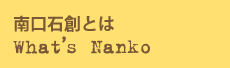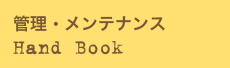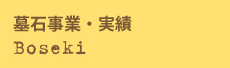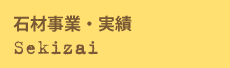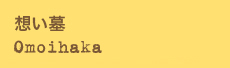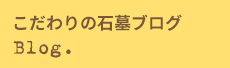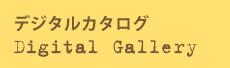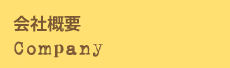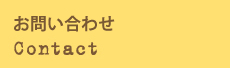ほほえみの「死」って、どんなもの?
死への不安をほどき、いまを生きるヒントを届ける
人は誰しも必ず死ぬ。まさに自分ごとなれど、あまりにも関心が薄いように思います。
対していかに生きるか、どう生きるかはメディアでも広く取り上げられ、本も多数出版され議論もされています。
特に「最近、”終活”という言葉を聞くけれど、なにをすればよいか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
「自分の充実した生」を考えるとき「自分の死」を真正面からとらえることにより人生に大切な意外な花の種のヒントがある。ゆくゆくは数々の花が咲き観ている人々に感動が湧き至福の時間が生まれる。
普段あまり考えない、考えようとしない死を考え、人生に活かしたいものです。
「死」の受け止め方の変遷
古代
自然と一体化した死生観が主流。神道の影響を受け、死後も魂が自然界と調和すると考えられていました。
奈良・平安時代
輪廻転生の概念により、死後の世界や次の人生のための修行が重視されるようになると同時に、極楽往生への願いが深まっていきました。
鎌倉~江戸時代
名誉や義理を重んじる武士の台頭により、「死を恐れない」という精神が強調され、死を自己の使命の延長として受け入れる文化が形成されました。
近代
西洋思想が流入し、合理主義や科学的な死生観が導入されました。一方で、戦時中には死を国家や集団のための犠牲として捉える反面、死が身近になることで死への恐怖も広まっていきました。
このように、以前は「死=怖いもの。忌み嫌われるもの」との考えが主流であり、タブー視されてきたといえます。

最近の死生観の変化
「終活」の登場
「終活」という言葉が広まったのは、2009年に週刊朝日で連載された「現在終活事情」がきっかけであるといわれています。
またその翌年にも、流行語大賞にノミネートをされています。
その原因としては、このようなことがあります。
- 少子高齢化が深刻になり、人々がより「老後」に関心を持つようになった
- 医療技術の発展により「治らない病気」が「治る病気」になり、死への恐怖が薄れていった
「死」を見つめなおす、新しい動き
死とあたらしく出会い直す『DEATHフェス』
『DEATHフェス』は、死をテーマとしたフェスを毎年開催しています。
2024年には10代から90代まで約2000人が訪れており、その輪は続々と広がっていっています。
死について明るく語り合う『終活スナックめめんともり』
日本初の常設終活スナックBar『めめんともり』はママたちや他のお客さんと、死についてオープンに語り合う場となっています。
ほかにも入棺体験など、死をポップに捉えるためのイベントを開催しています。
上記でご紹介したように、「死」を見つめ直すためのビジネスも登場し、その活動の輪は日本中に広がっています。
いまをどう生きるか
「死」と「生」
人生は山あり谷あり、困難に突き当たることばかりです。
そんななか、なぜ人は努力を重ねるのか。
それは、困難を克服したときの大きな達成感を忘れられないから。
命は無限ではなく、時間は限られた分しかありません。その限られたなかで、自分がこの世に存在していたという証を残したい。
心臓が止まったとしても肉体が朽ちたとしても、その人が生きていた証と意志は途絶えることなくのこり続けます。
輪廻転生という仏教的な視点でも、生物学的な視点でも「死」は終わりではなく、通過点なのかもしれません。
だからこそ人は後悔しないために今を生き、よりよい未来を掴もうとするのではないでしょうか。
ならば「死」は恐れるべきものではなく、今をよりよく生きるための助けとなるものなのかもしれません。

南口石創と歩む「生きること」の見つめなおし
「死」が「生きること」の見つめなおしなのであれば、お墓は亡くなった人のこれまでの人生を振り返り、感謝の気持ちを表し、その人やご家族にとっての新たな人生の歩みだしを後押しするものです。
従来よりの死生観もあれば、新しい動きの死生観もあります。
そして南口石創は、お墓の専門家です。
これまでたくさんのお客様とともに「死」に向き合い見つめなおし、数々のその人らしい、すばらしい生き方を教わりました。
だからこそ、お一人おひとりのお気持ちに寄り添ったご相談や考え方を共有し、共に歩むことが出来ます。
いま一度「死」を見つめなおし希望を掲げながら、皆様にとってのよりよい人生の一歩を踏み出してみませんか。
どんなに小さな不安や悩みの種も、みなさまとともに向き合ってまいります。
まずはお気軽にご相談してみませんか。