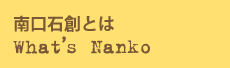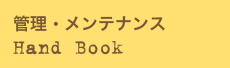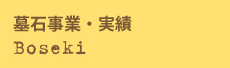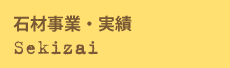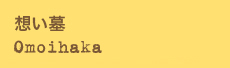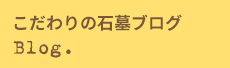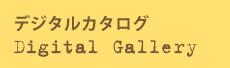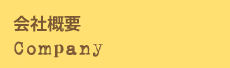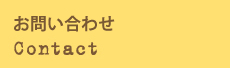「秋のお彼岸」だからこそ墓地整備を
真夏の暑さも少しずつですが落ち着きをみせ、夕方には涼しさを感じる季節となりましたね。
夏休みも明け、平日の朝から聞こえていた子供たちの遊ぶ元気な声が聞こえなくなったことに若干の寂しさを覚える、そんな今日この頃です。
この夏は、みなさまいかがお過ごしでしたでしょうか。
なぜ「秋の彼岸」にお墓参りにいくのか
今年の秋の彼岸はいつ?
そして今年も「秋の彼岸」がやってきます。
2025年の秋の彼岸は、9月23日の秋分の日を中心に、20日から26日の一週間です。
ところで、なぜ秋分の日に合わせてお彼岸にお参りに行くのか、ご存じでしょうか。
あの世とこの世が最も近づく日
春分の日・秋分の日は太陽が真東から昇り真西に沈むため、西方浄土(阿弥陀如来の極楽浄土)に通じやすい日と考えられています。
また昼の長さと夜の長さが同じになる日でもあることから、「あの世=彼岸」「この世=此岸」と近づく日でもあるのです。
この二つの世界の境界が接する日だからこそ、私たち此岸にいる人々が、彼岸から見守ってくれている故人さまに会いに行くのですね。
この時期に「墓地整備」をする理由3選
暑さが納まる季節
秋は太陽も陰りをみせ、長時間日光に照らされていても比較的心地よく感じる時期。
また夏には伸び放題だった草木も落ち着き、整備や工事がしやすくなります。
そのため、夏の雑草・台風の被害を整え、冬前に環境をリセットできる最適な時期ともいえます。

家族が集まる時期
家族や親戚一同が顔を合わせやすいこの期間は、大勢でお墓参りに行くことも多いはず。
その折にはやはり、普段は気がつかないお墓の傷みや雑草が目につきやすいでしょう。
また「細い山道や階段を上る必要がある」「お墓までの距離が遠い」など、お墓の立地や距離にも不便さを感じやすくなるかもしれません。
さらに「今あるお墓のこれから」について話し合う機会としても、よいといえるでしょう。
墓地整備だけでなく、墓じまいや手元供養、永代供養などについても考えるきっかけとなるはずです。
先祖への感謝
秋分の日23日は祝日です。
国民の祝日に関する法律では、この日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」日とされています。
あの世の故人さまとの距離が近づくこの日だからこそ、日頃の感謝の気持ちを改めて伝える、年に2回の特別な日ということですね。
墓地整備って、なにをするの?
墓地整備には、
・複数のお墓をまとめる
・お墓を移転させる
・雑草を生えにくくする
などがあります。具体的な内容は、過去のブログで詳しく解説しています。

この「秋の彼岸」だからこそ墓地整備を考えることをおすすめする理由がわかっていただけましたでしょうか。
しかし「なにから手をつけたらよいかわからない」、「ウチのお墓の場合は…」そんなご不安やお悩みもあるかと思います。
私たち南口石創では、電話での無料相談やお問い合わせをいつでも受け付けています。
お気軽にご相談してみませんか。
八芳園創業者に私達は何を学ぶのか
令和4年11月末、
長谷敏司翁顕彰碑の改修工事のご用命を承りました。
私はいつも「仕事を請け負う時」
1 何故その仕事がきたのか
2 発注者の思いはどうなのか
3 私は何のためにその仕事をするのか
をまず考えます。
しかし今回は、顕彰碑ということもあり、
長谷敏司翁の考えに想いを馳せるところから始めました。
佐治町出身の敏司翁は、東京での八芳園の創業、地元企業への出資・経営参画といった事業だけでなく、佐治村、県立高校等に多額の寄付をされ尽力された方。
その思いは、ご遺族に引き継がれ、今日の事業を発展させておられます。
また、奨学会の設立につなげ、若者の育成にも力を入れられています。その根幹にあるのは「人と未来」に対する無限の可能性への想い、と確信しました。
工事の年である令和5年は各事業の周年記念が重なる年です。顕彰石碑改修工事は、敏司翁の
想いを再発見する大仕事。つまり改修ではなく「再生」である。こう認識すると心が引き締まる思いがしました。
まずは石碑と対峙。
見えてきたのは多くの課題でした。
石碑と文字のバランス。
幅約1.7×高さ約2.5mという存在感のある石碑とそこに掘られた東大寺別当揮ごう文字。
両者を、どちらも負けない、そして、相互に引き立たせるための工夫が必要でした。
さらに、建立後46年の経年劣化。

正直に言うと、やりがいはもちろんのこと、同時にプレッシャーもあったと言わざるを得ません。
しかし、振り返ると名誉ある石碑再生に携われた事に感謝しかありません。
変色や石材中央部への表面汚れの浸透、石板の傾きやコケ、さらには顕彰説明文銅板についた黒錆対応などでした。
汚れを落とすことや傾きの修正は、苦労したものの、これまで培った技術でなんとか解決できました。
今回とりわけ注力したのは、この工事で顕彰石碑の価値をさらに高めることでした。
単に石碑の汚れを落とすのではなく、周囲の景観と同調しながらも存在感やメッセージ性を出すこと。
そのために5種類の薬品を試行錯誤しながら、汚れを取りつつ見た目の凹凸感を出すことでした。
太陽の動きとともに変化する石碑表面の影が動的な印象を与えることができるからです。
文字の彫りは土台の石碑との明度をはっきりさせることで石碑の大きさに負けないよう引き立たせ、仕上げに落款印に朱色を入れることで全体をキリッと見せました。
最終的には、里山を背景により力強く再生した顕彰石碑に敏司翁も喜んで下さっているのでは、と自負しております。

敏司翁の石碑を、それぞれの人が自分自身として何を思い、どう学ぶのか。
一度この名実ともに巨大な石碑と「対峙」してみてください。
今後、佐治のこの顕彰石碑が「人々に新しい可能性、未来への希望を抱かせる」聖地となり人々の「聖地巡礼」が行われる日々が来ることに夢を託します。